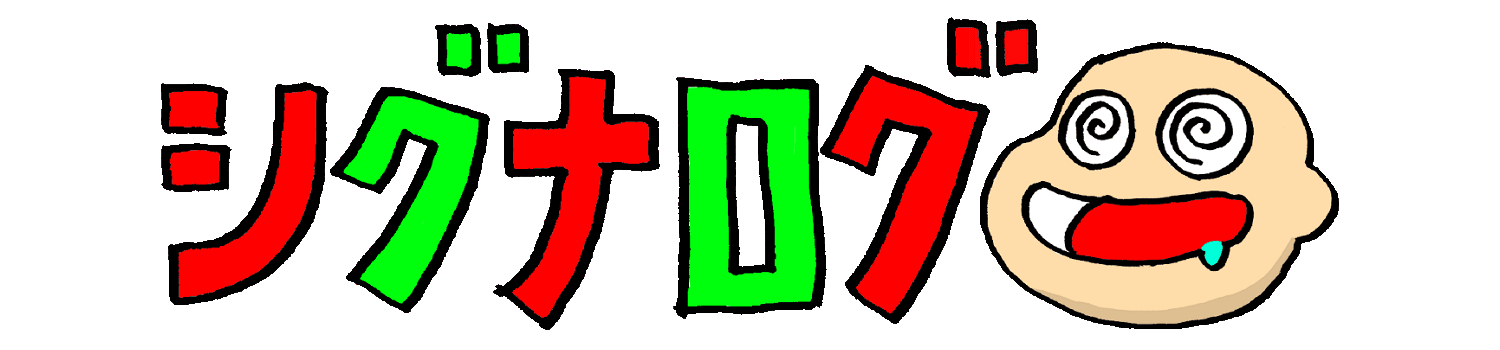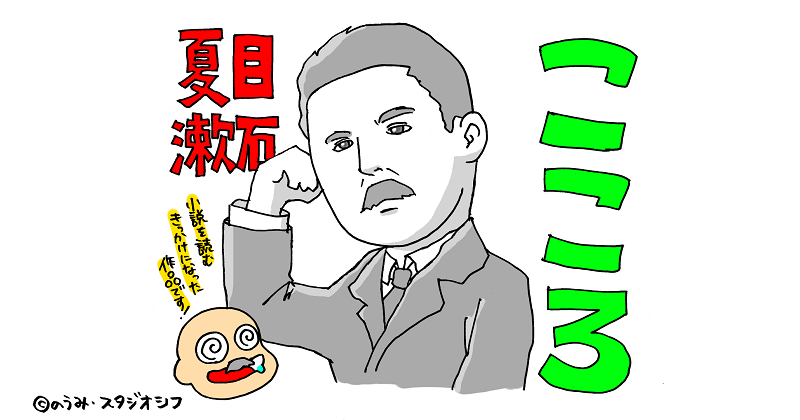
どうも、のうみです。
今はどうかはわからないけど昔は教科書に載っていた夏目漱石の「こころ」を紹介。
1914年(大正3年)に発刊されて100年以上前の小説とは思えないほど読みやすく、そして心に残る作品。
物語は三部構成で「先生と私」「両親と私」「先生と遺書」。
若干ネタバレのタイトルがありますが、そこは置いときます。
先生はどこか影のある存在だが、その行動や言動に学ぶべきことがあると思った私は徐々に交流を深めていく物語。
全ての人間の『こころ』に潜む光と闇の部分を露わにした作品
全ての人間の『こころ』に潜む光と闇の部分を露わにした作品
第一部「先生と私」では静かに暮らす先生と美しい奥さんとの関係、そして先生が毎月通う友人の墓参りのことが描かれています。
そして私は先生に、その教えを求めるあまり先生の過去に触れようとしますがこの時は拒絶される。
第二部「両親と私」では腎臓病を患った父親の病状が良くなく、親類が実家に集まり看病し見守っていた。
私は先生のいる東京には戻れず、しばらく実家で生活をすることになる。
そこへ先生から分厚い封筒が送られてくる。
第三部「先生と遺書」では先生からの封筒を開けた私は父のことが気になったが、すぐに東京行きの切符を買い電車に乗っていた。
分厚い封筒の中には先生の遺書が。
揺れる電車の中で静かに読み始めた。
そこには若かりし頃の先生と先生の奥さんともう一人、先生の友人である友人Kがいました。
読んだことのない人のことを考えてあらすじはここまで。
先生はなぜ死を選んだのでしょうか?
そして過去になにがあったのでしょうか?
それはあまりにも重く決して誰にも言えないでいた秘密なのですが、生前から交流を深めた私にのみに打ち明けた若かりし頃の先生が犯した罪と背負った罰。
それぞれの思いがすれ違い、そして疑念を生み、愛する人を奪われたくないという業がもたらした悲劇。
しかし、そういった業は誰にだってあるのではないのでしょうか?
先生も友人Kも悪人などでは無く、どこにでもいるありふれた普通の人間だった。
だからこそ、友情や愛を奪われることを恐れたのではないのでしょうか?
この結末は、果たして先生の罪はそれに似合った罰だったのか?
作品に唯一の救いがあるとしたらそれは、私へ先生の遺志が受け継がれたこと。
私とはこの物語の主人公でありそして読み手の私【あなた】でもある。
先生の遺志は読み手にも受け継がれるとは、この小説の底知れぬ力の凄さを感じます。